【出血性】脳機能障害(脳出血やクモ膜下出血)とは?後遺症に対する鍼灸治療!
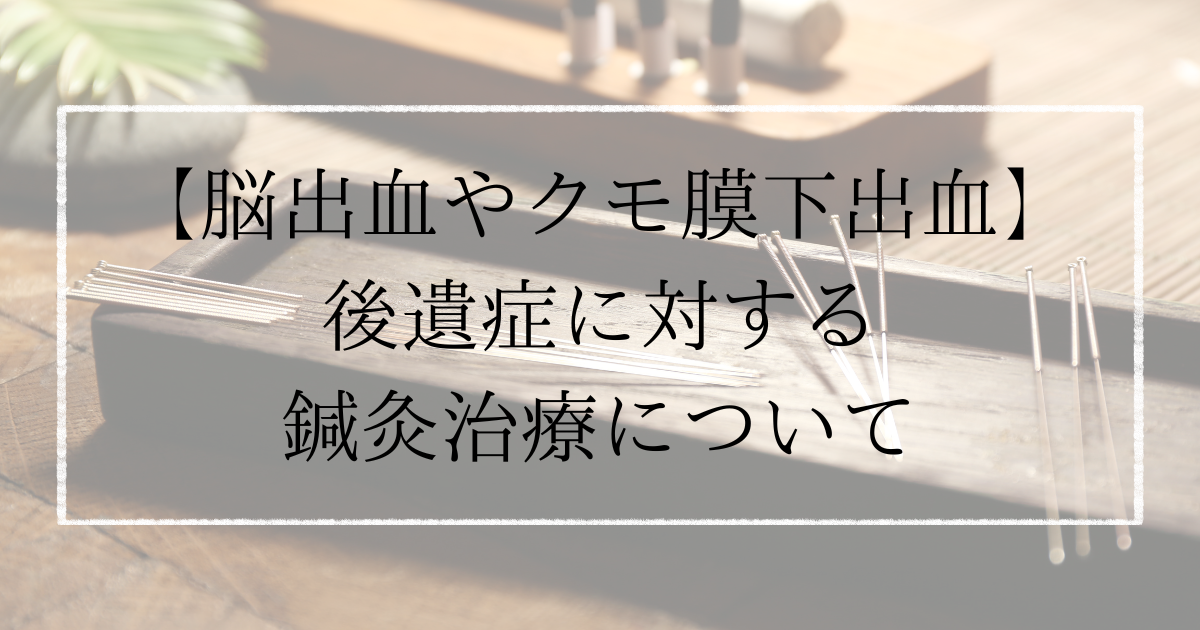
現在、日本において2020年の調査では、脳血管疾患の患者数はなんと174.2万人。
性別と年齢でみると、男性の70代(36.5万人)、女性の80代以上(36.1万人)での患者数が多くなっています。
実は介護保険が必要になった原因として、2番目に多い疾患なのです(ちなみに1番目は認知症)。
今後、ますます高齢化が進む中で、さらに増えていくと予想されます。
そこで重要になってくるのは・・・
もちろん、予防のための知識ですよね。
そして、脳機能障害になり後遺症が残ってしまった方へのケアの方法。
今回は出血性の脳疾患(脳出血やクモ膜下出血)に焦点を当てていきたいと思います。
この記事では・・・
・予防のための知識
・脳出血やクモ膜下出血の後遺症に対する鍼灸治療
について書いていきます!
特に、脳出血やクモ膜下出血などの後遺症で介護保険を受けられている方に、
今後、よりよい人生を送っていただけるように情報を発信していきたいと思います。
また、脳出血やクモ膜下出血の後遺症に悩まれている方に対しての訪問鍼灸をしていますので、
ご自宅でリラックスして鍼灸治療を受けていただけます。
ご興味があれば、お気軽にご相談ください(^^)
出血性の脳機能障害とは?~構造的なメカニズムとよくある症状~
では、そもそも出血性の脳機能障害(脳出血やクモ膜下出血)とは何か?についてです。
まずは構造的な話になりますので、

どこがどうなって後遺症が起こるんだろう?
と知りたい方はぜひ参考にしていただければと思います。
かなり長くなってしまっているので、
出血性脳疾患障害(脳出血やクモ膜下出血)になる原因や予防に関してだけ知りたい方は飛ばしていただいても大丈夫ですよ(^^)
脳出血(高血圧性脳出血)
昔は、脳いっ血と呼ばれていたものです。
今では一般的に脳出血と言われますが、実は正式には高血圧性脳出血なんです。
高血圧と付いているので、原因がわかりやすいですね(^^;)
そう、これは高血圧が原因で、脳の中の血管が切れてしまい、血液が脳の中に溜まってしまう疾患です。
脳出血~構造的な発生のメカニズム~
まず脳血管の構造はというと・・・
外から外膜→中膜→内弾性板→内膜
となっています。
加齢や持続的な高血圧によって、
まず中膜の平滑筋が線維化(石灰化)、
次いで内膜で血漿浸潤のため動脈壁の組織融解や
類線維素変性(フィブリノイド壊死)が起こり,
脳内小動脈瘤というものが形成されます。
この脳内小動脈瘤に血圧の上昇が加わると、血液が漏れ出し破綻します。
これが脳出血(高血圧性脳出血)の発生メカニズムです。
予防のカギとなるキーワード
・高血圧
脳出血になる元凶は高血圧!
なぜ高血圧になるのか?
これはよくテレビなどでよく目にするかもしれませんが、
あまり知られていない添加物の存在や高血圧に良い栄養素などもありますので、
後ほどに深堀っていきましょう!
脳出血でよくみられる症状
・突然発生する意識障害
・頭蓋内圧亢進による頭痛、吐き気、アニソコリア(左右の瞳孔の大きさが異なる)
・出血部位の反対側の運動麻痺
・眼球の血腫側への共同偏視(出血が前頭葉に及んでいると)
・失語症や構音障害(呂律が回らない)などの言語障害(出血部位による)
・高次機能障害
失行(身体機能に問題はないが、日常動作や道具の使い方などがわからなくなる)
失認(感覚器に異常はないものの、複数の感覚器を使って物体を認識できなくなる)
病態失認(自身の障害や病態に気づいていない)
脳出血の好発部位と部位別症状
被殻出血(レンズ核線条体動脈)
レンズ核線条体動脈とは、大脳基底核に血液を送る大事なところです。
症状としては・・・
反対側半身の運動障害・感覚障害
が起こります。
※被殻のみの出血であれば運動がぎこちなくなるだけですが、隣接する内包まで及ぶと重篤な運動・感覚障害が起こります。
視床出血(視床穿通動脈、視床膝状体動脈)
髪の毛よりも細い動脈なゆえに脆いです。
大事な動脈なのに脆弱なのは何故なのでしょうか(^^;)
症状としては・・・
意識障害
出血と反対側の感覚障害
完全~不完全麻痺
左右の眼球が内側下方を凝視
瞳孔の収縮
眼球が上へ向けない(垂直方向注視麻痺)
が起こります。
また視床膝状体動脈が出血を起こすと、視床症候群がみられるようになります。
※視床症候群の症状
→全身が痛む、しびれや感覚の違和感、コミュニケーションがうまく取れない、視界の一部が見えない、手足や顔が勝手に動く、など
皮質下出血(中大脳動脈)
脳の皮質と髄質の境界部近辺に走行している動脈が出血します。
頭頂部→側頭葉→前頭葉→後頭葉
この順に出血が多いとされています。
この部位の出血は、
微小動静脈奇形(先天性のもの)や細菌性動脈瘤(細菌感染のもの)、
アミロイド(タンパク質)などの血管壁への付着などが原因として起こりやすいです。
症状として・・・
頭痛
けいれん発作
出血側の共同偏視(前頭葉の場合)
単麻痺(運動野)
皮質盲(後頭葉)
てんかん発作をきたしやすい
※皮質下出血では、比較的に大きな血腫があった場合でも意識障害をきたすことが少ない
などが起こります。
小脳出血(上小脳動脈、後下小脳動脈)
ここが出血し第4脳室にまで大量の血腫が貯留すると、
髄液の動きが阻害されて水頭症が起こり、脳ヘルニアとなります。
ただちに手術にて血腫を除去することが一般的です。
症状として・・・
めまい(初期)
嘔吐(初期)
頭痛(初期)
起立、歩行困難(初期)
意識障害
処置が遅れた場合、最終的に亡くなります
などが起こります。
脳幹出血(前下小脳動脈、後下小脳動脈)
脳幹とは、中脳・橋・延髄・間脳で構成される中枢神経系で、
出血は橋で起こることが多いです。(といっても脳出血の中では稀)
この動脈らは脳底動脈から分岐するのですが、
脳底動脈からの穿通枝(細かい血管)の破綻によるものは、特に劇症です。
・高度の意識障害
・呼吸障害
・脳神経障害
・運動麻痺
また、脳幹には被蓋(脚橋被蓋核や腹側被蓋野)がありますが、
そこでの出血も重篤になりやすく、
・意識障害
・四肢麻痺
↑上記の症状に・・・
・顔面神経麻痺
・外転神経麻痺
が伴いやすい。
また、植物状態にもなりやすい部位です。
脳幹の出血がすべて予後が悪そうに見えますが、
場所によっては意識障害が起こったとしても一過性で、眼球運動の障害で済むものもあります。
脳幹出血が一側に偏っている場合は、
麻痺の現れ方は交代性片麻痺という型を取ります。
交代性片麻痺とは?
→上肢・下肢の麻痺に加えて、反対側の顔面神経麻痺を伴った状態。
クモ膜下出血
クモ膜下出血って聞くとすごく怖い印象がありますよね(^^;)
実際に恐ろしい疾患で、治療も困難だと言われています。
しかも、決して珍しい疾患ではないのです。
この疾患についてしっかり知ることは予防にもつながりますので、一緒に学んでいきましょう!
クモ膜下出血~構造的な発生のメカニズム~
脳を守るために、頭蓋骨の下から3層の膜に覆われています。
頭蓋骨→硬膜→クモ膜→軟膜→脳
この順に覆われていて、
今回の疾患は、クモ膜と軟膜の間にある「クモ膜下腔(髄液と血管が通る隙間)」にて起こります。
なんらかの原因によって血管(脳とつながる血管)が破裂し、急激に血液が髄液と混じりあい、クモ膜下腔全体に広がります。
この状態がクモ膜下出血です。
クモ膜下腔で血管が破裂したときは、



突然ハンマーやバットで殴られたような感覚!!!



今までに経験したことがないほど激しい
などと表現されるほど、突発的で衝撃的な頭痛が起こります。
クモ膜下出血の原因となるもの
・脳動脈瘤の破裂
・脳動静脈奇形の破綻
・脳出血
・頭を強く打ったりの外傷
・脳腫瘍からの出血
・白血病
この中でも、脳動脈瘤の破裂が80%で脳動静脈奇形の破綻が10%を占めています。
脳動脈瘤の破裂は40~60代が多く、
脳動静脈奇形の破綻は20~40代が多くなっています。
また、クモ膜下出血は男性に多く発症しています。
予防のカギとなるキーワード
・脳動脈瘤
クモ膜下出血にならないためには、
一番は脳動脈瘤にならないことです。
なぜ脳動脈瘤ができてしまうのか?
クモ膜下出血の予防はこれがカギになってきますよね。
後ほど見ていきましょう!
(脳動静脈奇形は先天性で、破綻は高血圧からきます)
クモ膜下出血のよくみられる症状は?
◇頭痛
これは先ほども書きましたが、
ハンマーなどの硬いもので思いっきり殴られたような衝撃、
味わったことがないほどに激しい、など。
クモ膜下出血の大きな特徴ですね(^^;)
◇項部の硬直
項部とは、うなじや後頭部のことですね。
早期から後頚部が痛いという患者さんは多く・・・
患者さんの頭を持ち上げると項部に抵抗感、激しい痛みを訴え、自動的に股関節や膝関節が屈曲します。
これをブルジンスキー徴候といいます。
ほかにも、顎と胸をくっつけることができない、額や顎を膝にくっつけることができないなども。
また、仰向け状態の患者さんの膝を持ち上げて伸ばそうとしても135°以上伸びない症状も現れます。
これをケルニッヒ徴候といいます。
この症状は・・・
出血や髄膜炎などの細菌による髄膜の科学的刺激、
脳圧亢進などの物理的刺激によって生じる筋性防御だと考えられているそうです。
◇四肢の運動麻痺やしびれ、感覚障害などの症状がみられない
脳の疾患というと・・・
運動麻痺、しびれ、感覚障害、意識レベルの変化、動眼神経麻痺などの局所神経脱落症状が起こるイメージですが、
クモ膜下出血では現れないのが特徴の一つです。
◇硝子体の出血
硝子体とは、眼球の中心を満たしているゼリー状の組織で、眼球の形を保つ役割などがあります。
クモ膜下出血が起こると、
その硝子体に頭蓋内の血液が視神経を通して流れ込み、
血液がゼリー状の中に混ざった状態になります。
これはターソン症候群ともいわれ、
出血が吸収されない場合は視力障害を残します。
目のかすみ、浮遊物が見える、視力の悪化などの症状があります。
クモ膜下出血後の1時間以内には発症するケースが多いですが、47日目まで発症が遅れたケースもあるそうです。
出血性脳疾患(脳出血、クモ膜下出血)になる原因と予防法
脳出血では高血圧が原因であることが多く、
クモ膜下出血では脳動脈瘤の破裂が原因であることが多いということでしたね。
これらを一つ一つ深堀していきましょう!
脳出血になる原因は、高血圧!
ある程度の年齢に差し掛かってくると気になりだしますよね。
この高血圧が脳出血の主な原因になります。
高血圧になる原因を深掘って気をつければ、脳出血のリスクも大幅に減らせますよ(^^)
まず、高血圧は「本態性高血圧」と「二次性高血圧」に分類されます。
9割が「本態性高血圧」で、生活環境(食やストレス)を改善すれば、ある程度コントロールが可能です。
一方で「二次性高血圧」は、糖尿病性腎症や大動脈弁閉鎖不全、ステロイドなど、特定の原因がわかっているものです。
なので、今回は本態性高血圧に関して見ていきたいと思います。
そもそも血圧ってどうやって計算されるかご存じでしょうか?
血圧の計算は以下の通りです(^^)
心拍出量×末梢血管の抵抗
心拍出量は、心臓が1分間に全身に送り出す血液量のこと。
末梢血管は、一般的に足や腕の血管のことを言います。
この両方が高ければ、血圧は高くなります。
・心拍出量が高くなる主な原因
→ストレスによる交感神経の亢進や塩分の摂りすぎによる体液量の増加
・末梢血管の抵抗が高くなる主な原因
→加齢による血管弾力性の低下、血管を拡張させる一酸化窒素(NO)の減少、血液がドロドロ、ストレスによる交感神経の亢進
このように血圧が高くなる原因はいろいろとあります。
でもこれだとマニアック過ぎて、日常生活で何を気をつければいいのか、何をしたらいいのかわからないですよね(笑)
それでは日常生活に照らし合わせて見ていきましょう(^^)/
高血圧になる原因
・喫煙
・肥満
・飲酒
・塩分の摂りすぎ
・ストレス
よく言われているのが上記の5つですよね。
ではなぜこれら5つが高血圧にしてしまうのか?
喫煙
言わずもがなですが、喫煙は血圧に影響が出ます(^^;)
タバコの煙には約4000種類以上もの化学物質が含まれており、
そのうち有害だとわかっているものだけでも200種類以上あるそうです。
その中の一つとして、ニコチンは交感神経を刺激して血管を収縮させる作用があり、これが血圧を上げる大きな要因です。
また、タバコには一酸化炭素(CO)が含まれていますが、
一酸化炭素は血液中の赤血球と結びついてしまうので、体内の酸素の量が減ります。
酸素の量が減ると、心臓は「もっと酸素を送らないと!」と心拍出量が増加し、血圧が高くなるということですね。



でも、タバコを吸うと落ち着くんだよな
そうですよね、
タバコを吸うとリラックスした感じもするし、落ち着く人もいらっしゃると思います。
それはドーパミンという快楽物質が関わっています。
報酬系ともいわれるほどで、メンタル面ではプラスに働いているように感じます。
しかし、体には良くありませんので・・・(^^;)
対策は・・・やめるしかありません(笑)
肥満
肥満と聞くと、体が横に大きい人や体重が重い人というイメージがありますが、
正しくは「体脂肪が過剰に蓄積した状態」のことです。
なので、一見、痩せていても肥満である可能性があるんです。
また、脂肪の付き方でも健康のリスクも変わってきます。
今回の高血圧になりやすい人の脂肪の付き方は・・・
内臓脂肪型(リンゴ型肥満)です。



ビール腹ともいいます。
男性に多いですね!
実は、女性に多い皮下脂肪型(洋ナシ型肥満)の人には、高血圧などの症状があまりみられません。
では、なぜ内臓脂肪型(リンゴ型肥満)の人が高血圧になりやすいのでしょうか?
それは内臓脂肪が蓄積されて血流が圧迫されるからです。
そのほかにも、塩分の摂りすぎやインスリンの過剰分泌などがありますが、
それについては後述しますね。
飲酒
飲酒による体に起こる作用は・・・
・交感神経の亢進
・コルチゾールやカテコールアミン濃度の上昇
・レニン・アンジオテンシン系(昇圧代謝系)が活性化
・血管平滑筋細胞内のカルシウム濃度上昇とマグネシウム濃度の低下
といったものが報告されています。
簡単に言うと、血管を収縮・狭窄する作用が多いです(^^;)
また、アルコールは利尿作用がありますよね。
利尿作用によって、体内から水分が出て行ってしまうので、
その分、血液がドロドロになってしまいます。
飲むときは飲みすぎないように、
水をしっかり摂りながらでしたらリスクも減りますよ!
塩分の摂りすぎ
これもよく聞きますよね。
でもなぜ塩分の摂りすぎが高血圧につながるのかを知っている人は少ないかもしれませんね。
知っておくと予防にも意識がいくので、深堀っていきましょう!
まず塩分を摂りすぎると、どのようにして血圧が上がるのか見ていきましょう(^^)
血中の塩分濃度が上がると・・・
1,血中のナトリウムの濃度が上がる
2,脳内のナトリウム濃度センサーが反応して交感神経を亢進させる
3,交感神経の亢進により、血管が収縮&血流量の増加
4,血圧が上がる
というような流れをたどります。
なんとナトリウムの濃度が上がると交感神経が亢進するんですね!
ちなみに交感神経が亢進すると血糖値も上がります(^^;)
一応、ナトリウムの濃度が上がったときには、
体内の均衡を保つホメオスタシスが働いて、
ナトリウムの濃度が上がった分、細胞や腎臓が水分で調節をしてくれますが、
もし腎臓が機能低下、もしくは不全に陥ってしまっている場合は
水分の調節がうまくいかず、高血圧のほかに全身のむくみや体重増加が現れます。
腎臓病で二次性高血圧になるのはこのためですね。



塩分を減らすしかないのか・・・
味の濃いものが好きなのに
すでに高血圧になっている方は、もちろん控えめにしたほうがいいです。
しかし・・・どうしても味の濃いものを食べたくなるときもあるでしょう(^^;)
そんなときは、なるべくカリウムを含むものも一緒に摂りましょう。
実は、カリウムは過剰になったナトリウムを排出する役割があるのです!
つまり、カリウムは血中の塩分濃度を下げてくれるんですね(^^)/
カリウムを多く含む食品
→バナナ、いちご、トマト、かぼちゃ、ブロッコリー、枝豆、ほうれん草、じゃがいもなど



なーんだ、じゃあコンビニで買ってきた枝豆と一緒に食べたら大丈夫か
と、思われるかもしれませんが!
市販でよくみられるある添加物には、カリウムを道連れに体外へ出て行ってしまうものがあるんです。
せっかく摂ったカリウムが流されてしまうんですね(^^;)
それが、リン酸塩です。
このリン酸塩は、どの商品に入っているか指定するのが難しいほど、本当にいろんな食品に入っています。
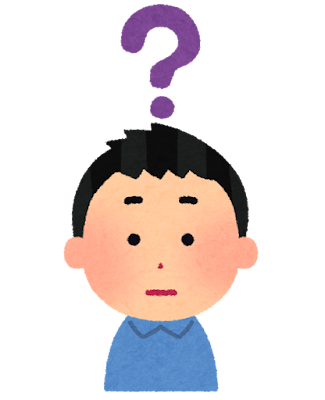
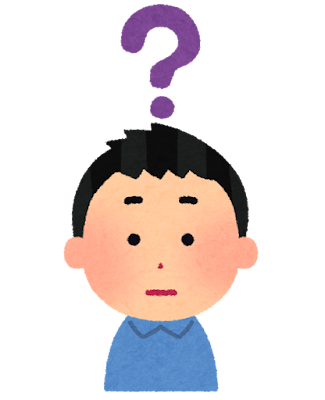
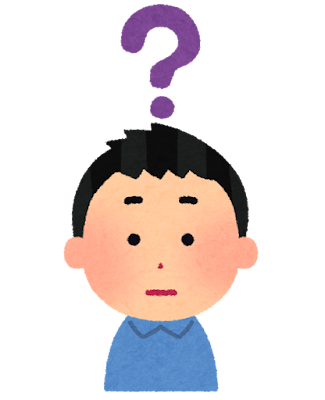
なら大丈夫なのでは?
私もそう思いたかったのですが、、、
リン酸塩の過剰摂取による骨密度の低下、腎臓疾患、治療力・免疫力低下、精神異常等など
こういった健康への影響が懸念されているんですよね(汗)
なので、できればリン酸塩を含まないものを食べてくださいね。
(含んでいるか確認するには、商品の裏にある原材料をチェックしてください)
ストレス
タバコも吸わない、お酒もあまり飲まない、塩分も気をつけているのに・・・
なぜか高血圧だという人もいらっしゃいます。
そういった方の高血圧の原因として考えられるのは、慢性的なストレスです。
ストレスは交感神経の亢進を促すので、血糖が上がり、血管が収縮し、血圧が上がります。
(血糖が上がると、体内の水分量が増えます。)
この反応は外敵から身を守るためのものですが、
現代社会ではいろんな要因でストレスが発生します。
特に幼少期からストレスの多い環境で育った方は、
常に交感神経がオンの状態が癖になっていて、様々な症状を引き起こします。
高血圧もその症状の1つですね(^^;)
いくら高血圧対策をしても、なかなか血圧が下がらないという方は、
ストレスの原因に関しての対策が必要かもしれません。
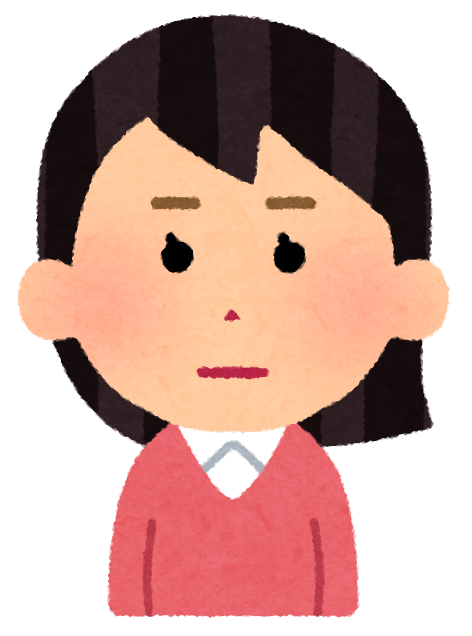
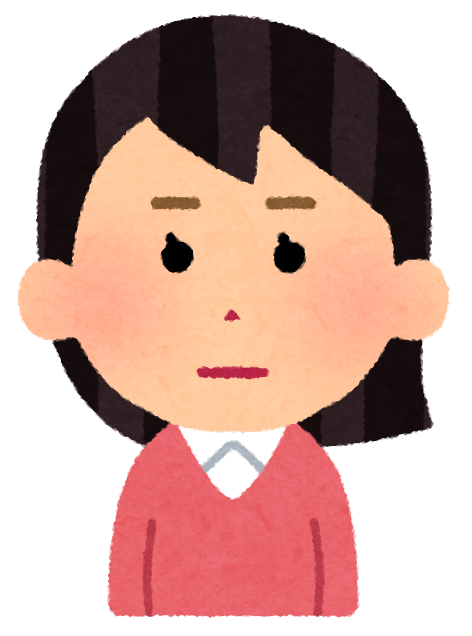
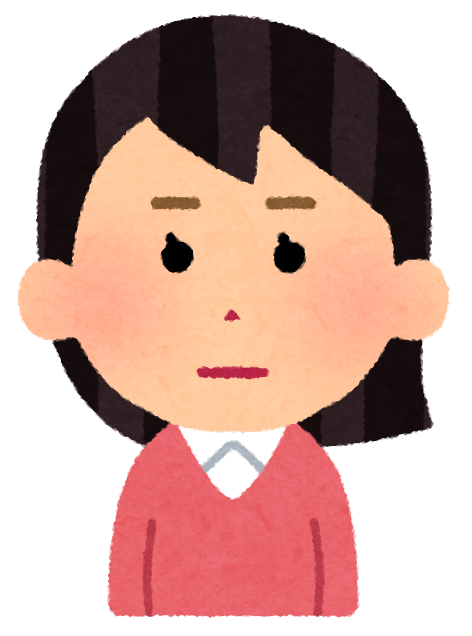
でも、思い当たるストレスなんてないのに…
という方は、
それこそ何らかの原因で交感神経がオンの状態が癖づいていると考えられます。
そういう方にこそ、鍼灸治療をお勧めしています(^^)
鍼灸は自律神経を整え、高血圧に関しての有意性があると研究でも報告されています。
ただ、もし鍼灸は怖いな、と感じられる方はカイロプラクティックや整体など、
自律神経を整えることができる療法もいいと思います。
ご自身に合った治療法をぜひ見つけてくださいね。
クモ膜下出血の原因の多くは、脳動脈瘤!
脳動脈瘤はクモ膜下出血の原因疾患として最多です。
脳動脈瘤ができる原因は一般的に、
先天的に血管壁が不完全な部分がある状態で血圧が上がり、
そこが風船のように膨らむことで脳動脈瘤ができると考えられています。
そのほかにも・・・
・動脈硬化による動脈瘤
・事故などによる外傷性の動脈瘤
・細菌感染による動脈瘤
などがあります。
その脳動脈瘤が破裂するのも、急激な血圧の上昇により起こります。



結局は高血圧が原因であることが多いということですね(汗)
出血性脳疾患(脳出血、クモ膜下出血)の後遺症に対する鍼灸治療
脳機能障害である脳出血やクモ膜下出血が発症し、
片麻痺などの後遺症が残っている方に対して、
当院での鍼灸治療ではどのようなことをしていくのかを説明させていただきます。
まず、脳機能障害の方に対して鍼灸で対応することが多いこととは・・・
・片麻痺(痙性または弛緩性)
・体の痛み(肩手症候群など)
などになります。
片麻痺
まず初めにお伝えしておかないといけないことは、
鍼灸で完全に片麻痺が治るわけではありません。
ただし、発症して30日以内の片麻痺の方が、YNSA(山元式新頭鍼療法)を受けて改善したケースはあります。
以下がそのデータです。
【発症して30日以内】
・著明改善:55%
・やや改善:31%
・改善なし:14%
【発症して6か月以内】
・著明改善:43%
・やや改善:38%
・改善なし:19%
【発症して1年以上】
・著明改善:14%
・やや改善:58%
・改善なし:28%
(引用:山元式新頭鍼療法の実践より)
また、理学療法士さんのリハビリと鍼灸を併用することで、
筋緊張の亢進が改善するケースも多く報告されています。
体の痛み(肩手症候群など)
脳機能障害の方の痛みは大きく分けて、中枢性と末梢性のものとがあります。
中枢性の痛み
まず、中枢性の痛みとは脳の機能が障害されることが原因で起こる「視床痛」のことを言います。
視床痛とは・・・
・焼き尽くされるような灼熱感や凍えるような凍結感
・チクチクとした痛み
・体の奥からうずくような痛み
・軽く触れただけでも激痛
といった、非常に耐えがたい神経障害性疼痛です。
痛みがずっと続いているような状況なので、
心身ともに疲れてしまう、でも眠れない。と訴える方もいらっしゃいます。
そのため自律神経が乱れ、食欲がなくなったり、便秘になったりと体のあらゆるところに問題が現れます。
そういった症状に鍼灸はアプローチが可能です。
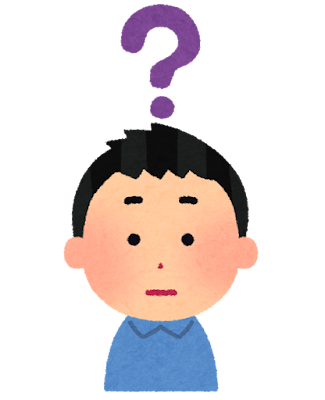
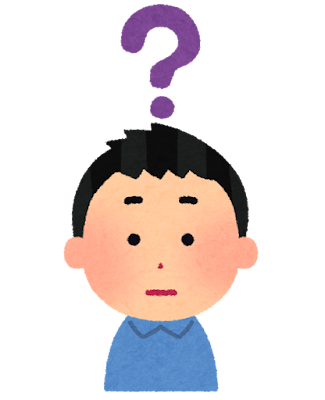
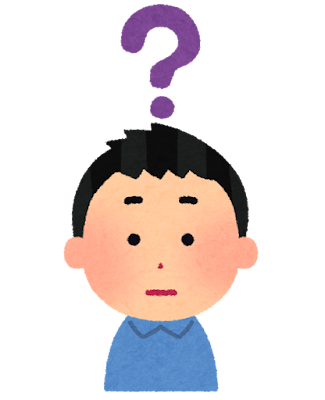
でも、触られるだけでも痛いなら、鍼灸も無理じゃない?
当院では経絡治療をさせていただいていますので、
「痛みがある部分」ではない箇所のツボを使用することが多いです。
なので、「触られたくない場所」は事前にお伺いして、無理のない施術を心がけています。
末梢性の痛み
末梢性の痛みとは、肩、腰、膝、頸部の運動痛や自発痛です。
脳機能障害の後遺症として「肩手症候群」が問題になりやすいです。
肩手症候群とは、
肩や手に疼痛、腫脹、熱感などが生じるもので、原因は不明だとされています。
肩手症候群があると痛くて動かせない、動かしたくなくなる原因となるため、リハビリがうまく進行できなくなります。
リハビリと鍼灸を併用することで、
痛みは鍼灸でアプローチして、リハビリの効率を上げることが可能です。
鍼灸で痛みにどうアプローチするのかは以下を参考にしてください^^
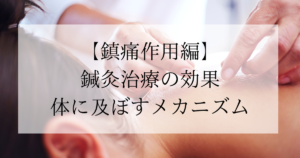
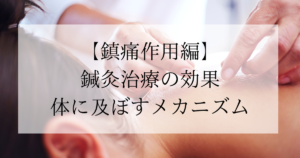
参考文献
・山本高穂,大野智:東洋医学はなぜ効くのか?
・矢野忠,川喜多健司:鍼灸臨床最新科学殻-メカニズムとエビデンス
・馬場元榖:絵で見る脳と神経-しくみと障害のメカニズム(第4版)
・鈴木郁子:やさしい自律神経生理学 命を支える仕組み
・山元敏勝(監),加藤直哉/冨田祥史(著):山元式新頭鍼療法の実践
・森ノ宮医療学園出版部:鍼灸OSAKA67号 特集 臨床シリーズ㊶脳血管障害後遺症
【この記事を書いた人】


大東市の訪問鍼灸~旭はりきゅう~
富永 旭人
・鍼灸師歴10年
・漢方養生指導士
・長野式鍼灸/YNSA/経絡治療
\ご予約・ご相談はコチラから/
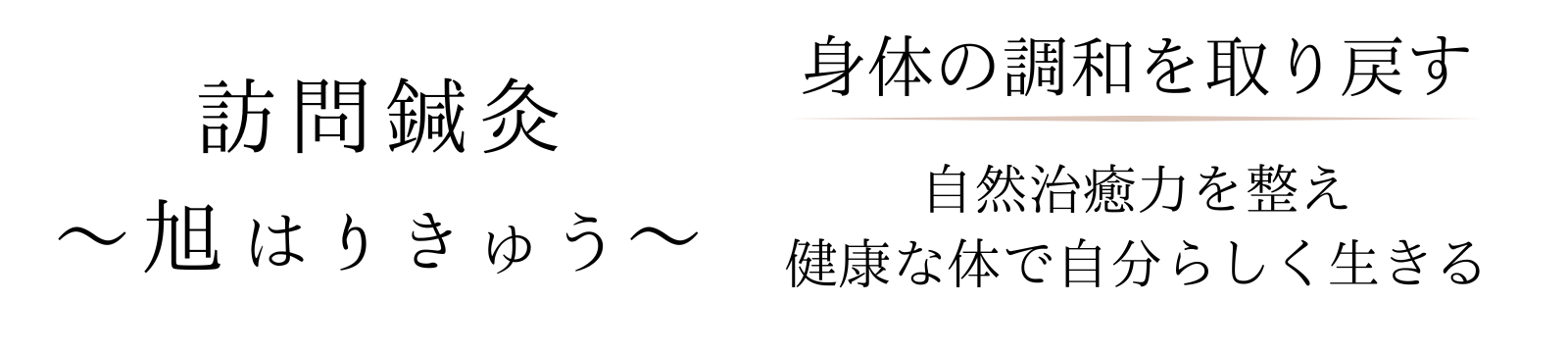
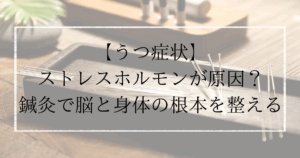
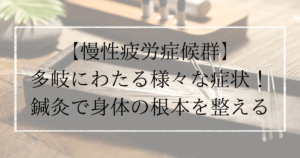
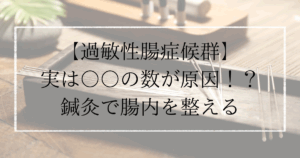
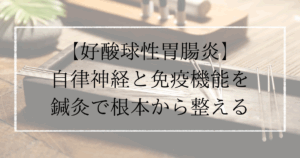
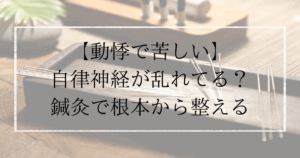
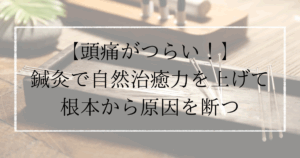
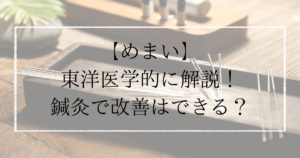
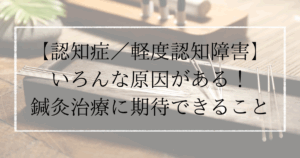
コメント