【閉塞性】脳機能障害(脳梗塞)とは?後遺症に対する鍼灸治療!
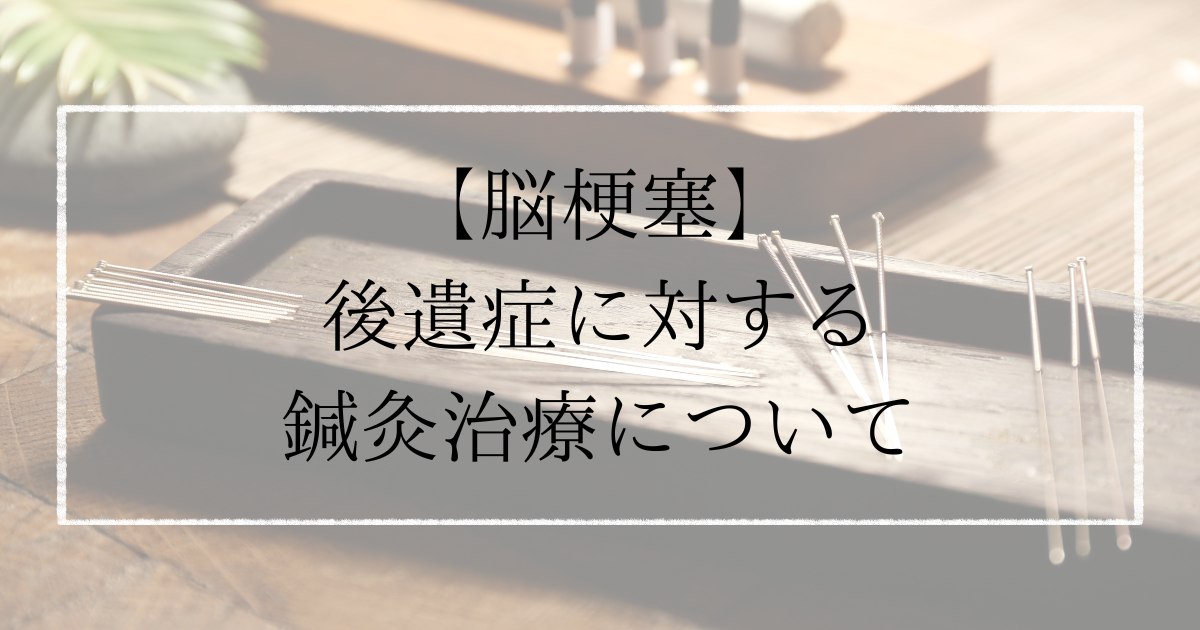
以前までは、「日本では脳出血が多くて、欧米では脳梗塞が多い」と言われていました。
しかし今では7:3の割合で脳出血よりも脳梗塞のほうが多くなってきており、
その理由としては食生活が欧米化しているからでは?など指摘されています。
これからますます増えると考えられますので、いかに予防するかが大切になってきます。
そのためにも脳梗塞に対する知識は重要なので、一緒に見ていきましょう(^^)
また、脳梗塞になり後遺症が残ってしまった方に対して、
「鍼灸治療はどう役立てるのか」をお話ししていきたいと思います。
当院では訪問させていただき鍼灸治療をしていますので、
ご自宅でリラックスしながら施術を受けていただけます。
ご興味がある方はお気軽にご相談ください(^^)
閉塞性の脳機能障害(脳梗塞)とは?~構造的なメカニズムとよくある症状~
それでは、そもそも閉塞性の脳疾患(脳梗塞)が何なのか?
構造的なメカニズムとよくある症状についてお話していきたいと思います(^^)
脳梗塞とは、簡単に言うと脳の血管が詰まってしまうことで起きます。
血管が詰まってしまうと、酸素やブドウ糖といった栄養が脳に行き渡らなくなり、脳細胞が壊死状態となります。
そして、意識障害、片麻痺、呂律が回らない、視界が狭いなどの症状が現れます。
脳梗塞は大きく3つの型に分けられます。
・アテローム血栓性脳梗塞
・ラクナ梗塞
・心原性脳塞栓症
アテローム血栓性脳梗塞
アテロームとは・・・
動脈の内膜にコレステロールや中性脂肪、カルシウム、白血球などが沈着した塊のことです。
生活習慣の乱れやストレスなどで、血管内に傷ができることで起こりやすくなります。
これが溜まると血管の中は狭くなり、弾力もなくなり、血流は妨げられてしまいます。
この状態が俗にいう動脈硬化ですね。
放置すると、完全に血管が閉塞した状態になります。
これがアテローム血栓性脳梗塞です。
内頚動脈、中大脳動脈、椎骨動脈など大きな動脈の起始部によく起こるので、重篤化しやすい傾向にあります。
ラクナ梗塞
ラクナとはラテン語で「小さなくぼみ」という意味で、
脳にある穿通枝という髪の毛くらいの細さの血管が閉塞することで起こるものを「ラクナ梗塞」と呼ばれています。
これもアテローム血栓性脳梗塞と同じように、動脈硬化が原因で起こります。
ラクナ梗塞の場合、小さな血管で起こるので気づかないまま進行する恐れもあります。
もし気づかないままラクナ梗塞が多発すると、
「記憶力の低下が目立つに、理解力や判断力はしっかりしている」という
”まだら認知症”が見られるようになります。
他にも、頭痛やめまい、耳鳴り、手足のしびれなど軽度の症状から
よくつまずくようになった、呂律が回らない、やる気が出ない、感情の浮き沈みが激しいなど・・・

今日はちょっと調子が悪いな・・・
と見逃してしまいそうなものが、ラクナ梗塞による症状の可能性もあります。
ほとんど自覚症状がないので注視されることが少ないのですが、
これが放置されると・・・
重大な脳梗塞のリスクが約10倍以上にまで高まります。
記憶力の低下、頭痛やめまい、手足のしびれ、言葉を発しにくい、つまずくことが増えたなど、
これらの症状が多数現れた場合は、なるべく早めに検査を受けることをおすすめします。
といっても一番大切なのは、食生活などの日常生活を見直すことですね(^^;)
それについてはまた後述しますね!
心原性脳塞栓症
心臓でできた血栓(血の塊)が脳まで運ばれ、脳の血管を詰まらせてしまうものです。
突然発症して重症になりやすいことから「ノックアウト型脳梗塞」と言われています。
その原因の多くが心房細動。
なのでまずは心房細動に気をつけることが、心原性脳塞栓症の予防になります。
心房細動とは、心臓の心房というところが十分に収縮せずに、
けいれんするように細かく震えることで脈が不規則になるものです。
心房細動になる原因は、心臓の異常な電気興奮です。
つまり、交感神経の異常な亢進ですね。
症状としては、動機、息切れ、倦怠感、めまい、胸の不快感などがあります。
交感神経の異常な亢進が起こる理由はいろいろとありますが、
ストレス、高血圧、喫煙、飲酒などですね。
ほかにも、糖尿病や睡眠時無呼吸症候群によるものもあります。



生活習慣の乱れが大きく影響していると考えられますね。
なかには、生活習慣を改善しても交感神経の亢進が収まらない方もいらっしゃいます。
それは何らかの原因(たとえば幼少期のストレスなど)で、
交感神経の亢進が癖になってしまっている可能性があります。
たとえば、電話が苦手な方はコール音だけでも激しい動悸がします。
その電話内容がどんなに安全なものだったとしてもです。
これは電話に対するトラウマがあるからだと考えられますが、
無自覚にこのようなトラウマを積み重ねてしまうと、
何でもない日常生活にでも体が勝手に反応してしまうんですね(^^;)
もちろん、自覚があってPTSD(心的外傷後ストレス障害)を持っているなどの原因がわかっている場合はカウンセリングなどで対処できますが・・・
そうでない方が大半かと思います。(近年ではこれを複雑性PTSDと呼ばれることも)
そういった自律神経の乱れに対して、鍼灸治療がお役に立てる場合もあります。
メカニズム(科学的根拠)に関しては、別の記事に記載していますので、
ご興味があれば一読いただければと思います(^^)
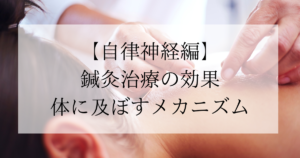
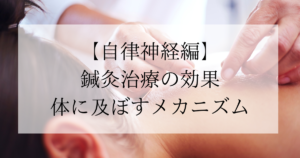
閉塞性の脳機能障害(脳梗塞)になる原因と予防法
ざっと脳梗塞について一緒に見ていきましたが・・・
・動脈硬化
・交感神経の異常な亢進
以上の2つが大きな原因となりやすいことがわかりましたね。
これらが起こる原因をさらに深堀っていくことで脳梗塞の予防となりますので、1つずつ見ていきましょう(^^)
その前に、動脈硬化のメカニズムを簡単に見ておきましょう!
わかりやすく書いてある記事がありましたので、そのまま引用させていただきます。
(1)内皮細胞に傷がついた際、血中のLDLコレステロールが多いと、損傷した部分から内皮細胞の内側に入り込みやすくなる。
(2)内皮細胞と血管壁の間に入ったLDLコレステロールは酸化されて、体に不要な酸化LDLへと変化する。
(3)酸化LDLは毒性を持つため、排除すべき異物とみなされる。すると、免疫細胞のマクロファージがやってきて、酸化LDLを食べるが、酸化LDLが過剰にあると、食べきれずに死んでしまう。
(4)血中にLDLコレステロールが多い場合はこの反応を繰り返し、内膜の内側でこの「プラーク」(マクロファージが死んでできた、かゆ状のもの)が肥大化していく。
(5)さらにこの際、「線維化」と呼ばれる組織が硬くなる現象が起きるため、動脈の柔軟性が失われてしまう。
動脈硬化になる仕組みと対処法について
LDLコレステロールとは、悪玉コレステロールのこと。
つまり、動脈硬化は悪玉コレステロールが多すぎると起こる現象だということですね!
ということは、動脈硬化の予防で一番気をつけないといけないのは・・・
血中の悪玉コレステロールの増加です。
「悪玉コレステロールが増加する原因」と「交感神経が亢進する原因」は似ているところが多いので、まとめて見ていきましょう(^^)/
喫煙
実はタバコが燃えるときに出る一酸化炭素が体内に入ると、
血液中の悪玉コレステロールが増加し、善玉コレステロールが減少することがわかっています。
また、タバコに含まれるニコチンは交感神経を刺激し、心拍数や血圧が上昇します。
なのでタバコを吸うと、一酸化炭素とニコチンによって悪玉コレステロールが増加し、交感神経が亢進するんですね(^^;)
そのほかにもタバコの有害化学物質は200以上あり、血管を傷つける物質も存在することから、
余計に悪玉コレステロールが血管に入り込みやすくなります。
つまり、脳梗塞になる可能性を上げてしまいます。
なのでタバコはなるべく控えたほうがいいですね。
飲酒(つまみ)
飲酒に関しては、むしろ適量なら悪玉コレステロールを減らすと言われています。
実際、私の92歳の患者さんは毎日お酒を1~2杯飲んでいます。
でも、適量が一番難しいですよね(笑)
具体的に適量というのは、純アルコール量で20g程度が目安。
ビールなら中瓶かロング缶1本、
日本酒なら1合、
ワインなら2杯、
ウイスキーなら水割りダブルで1杯。
以上が適量とされています。
この適量のあたりぐらいで控えるのが一番いい飲み方!
しかし、この辺からホロ酔いになって、もっと飲みたくなるんですよね(^^;)
もう少し飲むために・・・せめて、これだけは気をつけよう!というのが、
つまみです。
ついつい脂っこいもの、塩辛いものを食べてはいませんか?
確かに脂っこいものを食べると、しばらく胃に滞留するので、急激な酔いを防いでくれる話もありますが、、、
それによって飲みすぎてしまう原因にもなるし、
シンプルに中性脂肪が増えて、血中の脂によって動脈硬化が進行します(^^;)
それに、アルコールは水分を減らすので、血もドロドロになりやすくなります。
脂が増えたり血がドロドロになるのは怖いですよね。
また、過度な飲酒は交感神経を刺激して、自律神経を乱します。
お酒を飲んだら、いつもより陽気になる人は多いですよね。
それは飲酒によって体内のドーパミンやセロトニンが分泌されて交感神経が上がることで起こる現象です。
たまになら問題ありませんが、
これが毎日になると交感神経が過剰になり、自律神経が乱れてしまいます。
ちなみにですが、
逆に喧嘩っ早くなるのは、アルコールによって理性を保つ前頭前野の働きが鈍くなり、
感情をあらわす大脳辺縁系が活性化することから起こる現象です。
怒りの感情をため込みすぎている人に起こりやすいかもしれませんね(^^;)
少し話がずれましたが・・・
まとまると、適度な飲酒はオッケーです!
ただし、つまみは脂っこいものをなるべく避けて、飲みすぎないようにしましょう!
余談ですが、赤ワインのポリフェノールには抗酸化作用があって、動脈硬化の予防に効果があるそうですよ(^^)
ホルモンバランスの乱れ
これは女性特有の現象になります。
もともと女性ホルモンの「エストロゲン」には善玉コレステロールを生成する働きがあり、
余分になった血中の悪玉コレステロールを回収して肝臓にまで運んでくれます。
しかし、40~50代頃に更年期を迎えると、「エストロゲン」は急激に減ってしまいます。
それによって、血中の悪玉コレステロールが量が増えてしまうんですね。
脂肪もお腹まわりにつきやすくなったりと、体に変化も生じます。
また、「エストロゲン」は自律神経のバランスにも貢献していて、
特に副交感神経の活動をサポートしています。
なので、「エストロゲン」が減少してしまうと、交感神経が上がりやすくなり、自律神経も乱れやすくなってしまいます。
では、「エストロゲン」を減らさないためにはどうすれないいのでしょうか?
それは、植物性エストロゲンをしっかり摂取することです!
大豆、納豆、豆腐、厚揚げ、きな粉などの大豆製品ですね(^^)
また、かぼちゃやアーモンドなどのビタミンEが多く含まれているものは、
ホルモンバランスの調整などの役割をしてくれるので、一緒に摂取しましょう!
(参考記事:更年期を明るく過ごそう!上手に乗り切る食生活のポイント)
ストレス
一般的にはあまり話題にはのぼりませんが・・・
実はストレスによって悪玉コレステロールは血液中に増えます。
なぜ増えるのかというと、
体はストレスに対応するために交感神経を上げて副腎皮質ホルモン(コルチゾール)を放出するのですが、
その材料になるのが悪玉コレステロールなんです(^^;)
なので、ストレスが慢性になればなるほど、悪玉コレステロールは血中に増えます。
また他にも、血糖値が上がったり、血圧が上がったりと体の影響は多く・・・
本当にストレスには気をつけたいですね。
閉塞性の脳機能障害(脳梗塞)の後遺症に対する鍼灸治療
閉塞性の脳機能障害である脳梗塞が発症し、
片麻痺などの後遺症が残ってしまった人に対して、
当院ではどういった鍼灸治療をしていくのかを説明させていただきます。
・痛みがあってリハビリができない
・筋肉の拘縮がある
以上の方に、
鍼灸治療で改善できる可能性があります。
痛みがあってリハビリができない
脳機能障害の後遺症での痛みは・・・
・焼かれるような灼熱感、凍えるような凍結感
・チクチクとした不快な痛み
・疼くような骨からの痛み
・軽く触れただけでも激痛がある
という中枢性の痛み(視床痛)があったり、
・動かそうとすると痛みがある
・腫れたり熱感がある
・しばらく動かしていなかったため痛みがある
以上のような末梢性の痛み(肩手症候群や廃用症候群)がある場合があります。
このような痛みがある場合は、回復期のリハビリが難航することが多く、
そうなると筋力や認知機能の低下の恐れが高くなり、次第に日常生活が難しくなってしまいます。
そうならないためにも、後遺症の痛みはうまく対処する必要があります。
その痛みを対処する方法の一つとして、鍼灸治療は著効を示すケースが多くあります。
今では鍼灸の「鎮痛作用」に関する研究結果や科学的根拠なども解明されています。
・血流が良くなり、体内の発痛物質が流れる
・免疫細胞から内因性オピオイド(鎮痛成分)が分泌される
・鎮痛作用に関わるA1受容体が生体エネルギーと結合する
・脳の扁桃体を抑制して、不安などによって増強された痛みが改善
以上の4つが現段階でわかっている鍼灸による鎮痛作用です。
このように脳機能障害の後遺症の方に対して、
痛みを和らげてリハビリの援助、ADL(日常動作)の向上のお手伝いをさせていただくことが可能です。
詳しくは以下の記事にまとめています(^^)
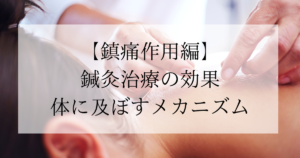
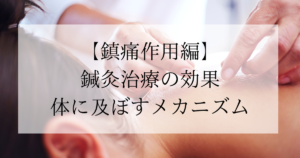
筋肉の拘縮がある
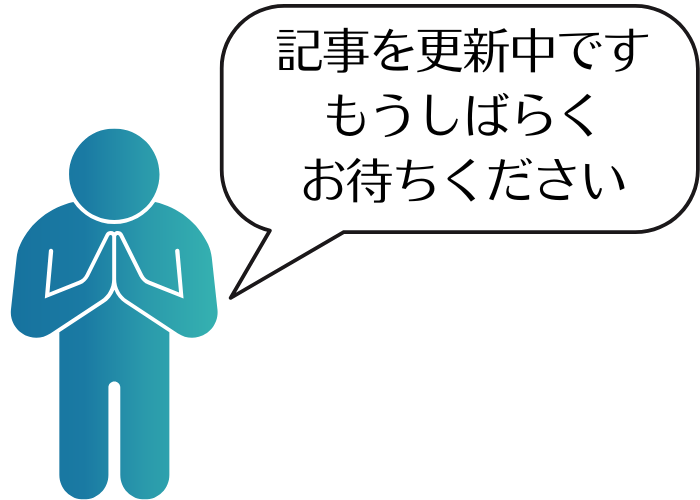
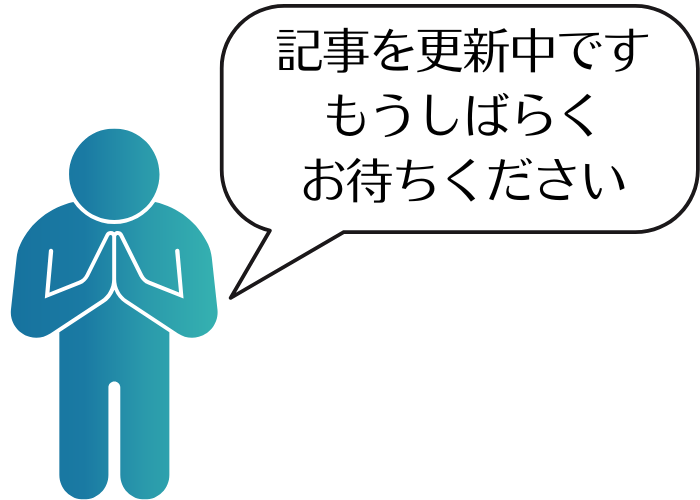
参考文献
・山本高穂,大野智:東洋医学はなぜ効くのか?
・矢野忠,川喜多健司:鍼灸臨床最新科学殻-メカニズムとエビデンス
・馬場元榖:絵で見る脳と神経-しくみと障害のメカニズム(第4版)
・鈴木郁子:やさしい自律神経生理学 命を支える仕組み
・山元敏勝(監),加藤直哉/冨田祥史(著):山元式新頭鍼療法の実践
・森ノ宮医療学園出版部:鍼灸OSAKA67号 特集 臨床シリーズ㊶脳血管障害後遺症
【この記事を書いた人】


大東市の訪問鍼灸~旭はりきゅう~
富永 旭人
・鍼灸師歴10年
・漢方養生指導士
・長野式鍼灸/YNSA/経絡治療
\ご予約・ご相談はコチラから/
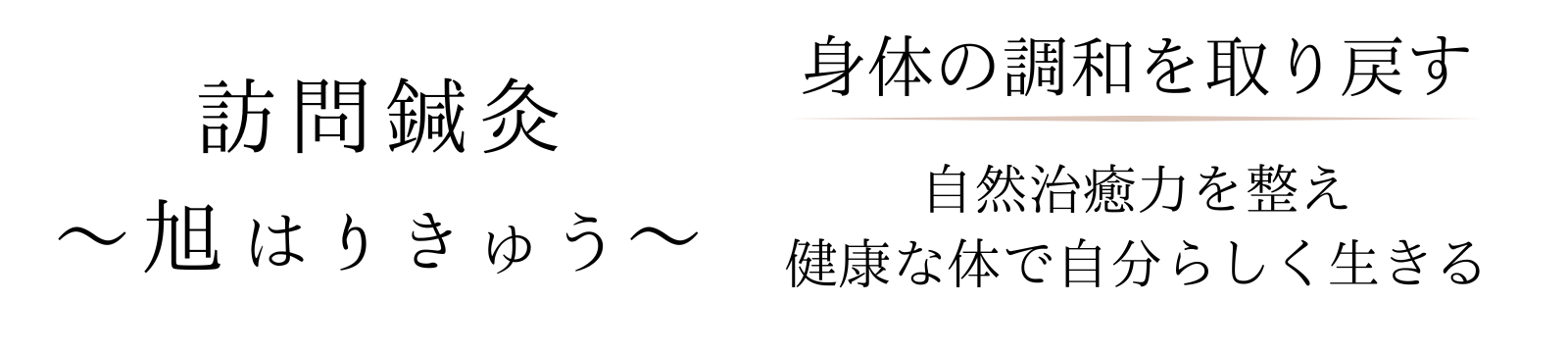
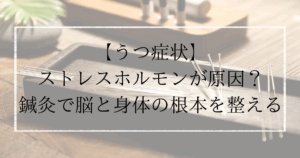
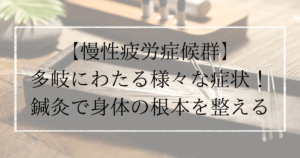
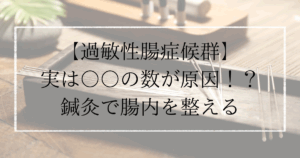
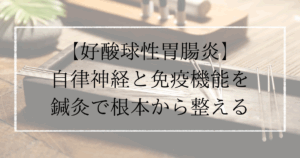
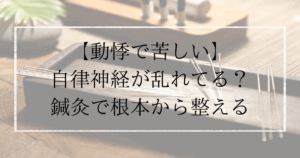
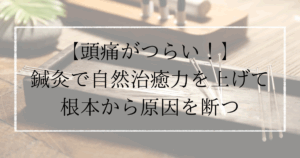
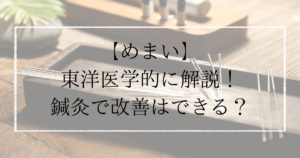
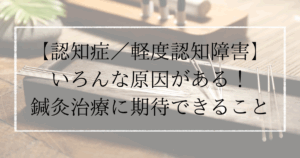
コメント