東洋医学の五臓と感情は密接に関係している!
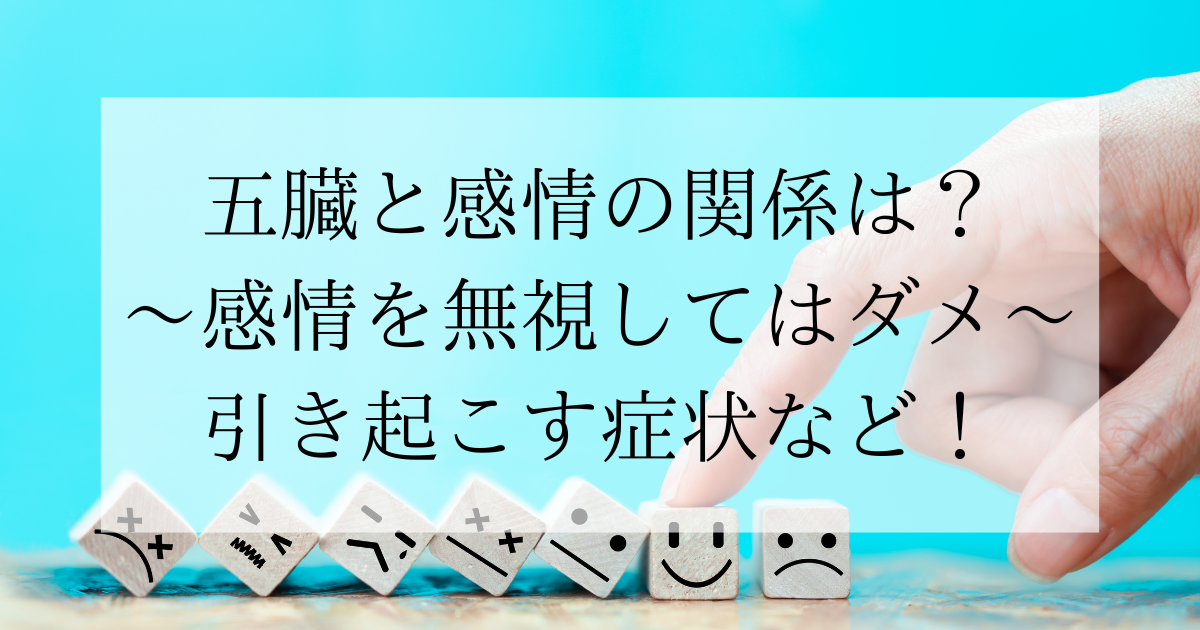
東洋医学では、古くから身体と感情の結びつきを伝えられていて、
長期間または急激に特定の感情が発生すると、五臓に影響を与えるとされています。
五臓に影響を与えるとされているのは、
喜・怒・憂・悲・思・恐・驚の七つの感情で、これをまとめて七情といいます(^^)
どの感情がどの五臓に影響を与えるか?は以下になります!
肝→怒
心→喜
脾→思
肺→憂・悲
腎→恐・驚
繰り返しになりますが、
五臓に影響を与えるのは「長期間または急激に起こる感情」です。
”急激に起こる感情”は、事故や突然の精神的なショックのことで、
”長期間にわたる感情”は、育った環境や、長年精神的に負担のかかる環境での生活によってつくられた、感情の癖や無意識レベルで定着しているものによるものです。
「感情を出さないほうが病気にならない」ということを言いたいわけではなく、
正常な範囲で感情が起こることは悪いことではなく、むしろ正常な感情は身体にとってはいいんですよね(^^)
しかし、逆に日本人は感情に蓋をして必要以上に我慢をすることが美徳に感じる風潮にあるので、
感じるはずの感情を感じることが出来なくなっている人は多くなっているように感じます。
なので、無意識に特定の感情によって五臓を害している可能性もあります。
だからといって「感情をフルパワーで出して自分勝手に生きたほうがいい」というわけではなく、
解消されていない一つ一つの感情と向き合い、原因となるものを解決できれば、それが最善策だと思います(^^)
話が少しそれましたが・・・
今回は、それぞれの七情が与える五臓への影響について解説していきます!
五臓と関連が深い感情は七つ!
先ほどもお伝えしましたように・・・
五臓に影響を与える感情は七つ、「喜・怒・憂・悲・思・恐・驚」です!
これらの感情が与える五臓への影響について解説していきますね(^^)
肝→怒

「怒る」という感情は「気」を上昇させる特徴があり、
「肝」も「気」を外向き上向きに上昇させる作用があります。
なので、もともとは「怒」は「肝」が持つ正常な感情ですので、
正常に働けば「積極的・計画的・徹底的・潔癖」な精神状態を保つことが出来ます。
この感情は「血」を多く消耗するので、
何らかの影響によって過剰(怒りすぎ)になってしまえば、
「肝」の「血」が不足してしまって「肝虚」という状態になります。
逆に、家庭環境などが原因で「怒りたくても怒れない状態」で我慢してしまうと、
「血」が停滞してしまって「肝実」という状態を引き起こし、鬱っぽくなります。
引き起こす症状は?
・怒りすぎ→不眠、めまい、耳鳴り、頭痛、けいれんなど
・怒りを我慢→イライラ、喉の異物感、倦怠感、抑うつなど
心→喜

「喜」は「心」の正常な感情で、「気」を緩める作用があります。
また、「心」が持つ陽気の性質によって「おおらかでにこやか」な精神状態を示します。
なので、正常な時は気持ちも和らいでリラックスした状態になります。
しかし、喜びすぎると「心」に熱が多くなりすぎて、
不整脈や動機、ひどいと失神を引き起こすこともあります。
逆に何らかの影響で「心」に熱が多くなりすぎると、
「喜」の感情が過剰になってしまいます。
そうなると・・・深刻な場面でも異様に明るい、どんなときでも受け答えが明るすぎる、という状態になります。
何でも「明るい」は良いと思われがちですが、「心」に熱が多すぎる状態にある可能性もあるので、以下の症状がある場合は注意が必要です(^^;
引き起こす症状は?
喜びすぎる→動機、不眠(入眠困難)など
脾→思

「思」は「脾」の正常な感情で、「気」を滞らせる作用があります。
「脾」の飲食物から「気」や「血」を作り出す性質によって、
「思考する・思慮が深い・考えを巡らせる」という精神状態を示します。
「脾」や「胃」で作られた「気」や「血」などで頭を働かせたり、人に気を回したりと精神活動をしますので、
正常なときは、記憶力が良く思考力があり、落ち着いて物事を考えることができます。
なので、もし「脾」の働きが悪くなって「気」や「血」の供給が少なくなると、考えがまとまらなくなります。
逆に、日常において考えすぎや思い悩むことが多くなると、
「気」の循環が悪くなり「胃」も働きにくくなって、食欲がなくなります。
引き起こす症状は?
思い悩む・考えすぎ→食欲不振、腹痛、下痢など
肺→憂・悲

「憂」は「肺」の正常な感情で、「気」を集める作用があり、
「肺」の内に収める性質によって「静かで孤独」という精神状態を示します。
また、「憂」が過ぎると「悲」の感情が深くなりますが、「悲」は「気」を消耗します。
「肺」の機能が低下すると、憂い悲しむという感情に陥りやすくなり、
逆に、憂い悲しむような出来事が多いと「肺」の機能が低下してしまいます。
そうすると、一人で行動できない、声が小さくなる、または風邪っぽいなどの症状が現れます。
さらに憂い悲しみが深くなると、「肺」に熱がこもり、喘息や咳などが起こります。
「肺」に熱がこもったときは、愚痴を言うことで「気」を発散させることができるので、
最近、急に愚痴が多くなった!などがあれば、
もしかしたら「肺」に熱がこもっているのかもしれません(^^;
引き起こす症状は?
憂い悲しみすぎる→声が小さくなる、喘息、咳など
腎→恐・驚

「恐」は「腎」の持つ正常な感情で「気」を下降させ、
「腎」の陰的な性質によって「謙虚な」状態を示します。
実際に「腎」がしっかりしている人は、他人と争うことなくどっしりと構えている人が多いそうです(^^)
しかしそんな人でも、恐れるような出来事が多いと腎虚になり、必要以上にオドオドしたり、遠慮しすぎたりするようになります。
逆に、何らかの影響で腎虚になっても、恐れやすくなります。
また「恐れ」と同時に「驚き」が起こることはよくありますが・・・
腎虚になると、さらに些細なことでも驚きやすくなります。
引き起こす症状は?
恐れ驚きすぎる→些細なことで恐れたり驚く、動悸、失禁、ひきつけなど
以上が、感情が与える五臓への影響についてでした!
昔からの言葉では「気が動転する」「悲しくて気が塞ぐ」「気が動転する」「怒りで逆上する」など、
感情が与える「気」の動きから言葉が作られています(^^)
現代では、感情が与える身体の影響があまり認知されていないからなのか・・・
簡単に人を傷つけるような言葉を言ったり、ネット上に上げる人も多くなりましたね(泣)
それだけではない、もっと闇が深い部分もあるかもですが(^^;
感情(ココロ)が身体に与える影響は絶対にあるので、あまり自分のココロや感情を無視しないようにしていきたいですね!
何か参考になりましたら幸いです!
【この記事を書いた人】

大東市の訪問鍼灸~旭はりきゅう~
富永 旭人
・鍼灸師歴10年
・漢方養生指導士
・長野式鍼灸/YNSA/経絡治療
\ご予約・ご相談はコチラから/
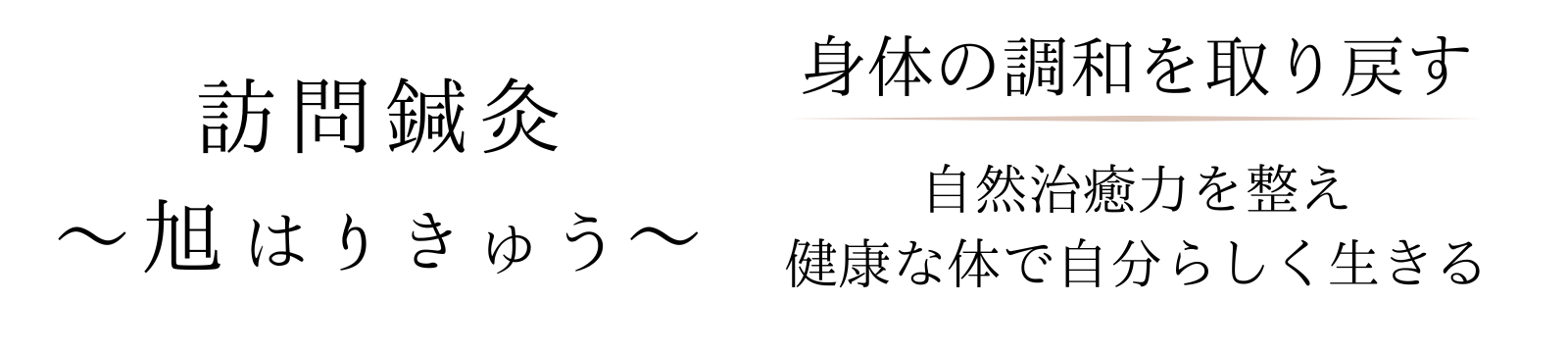
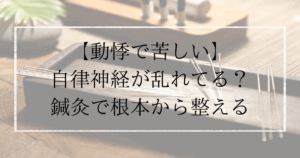
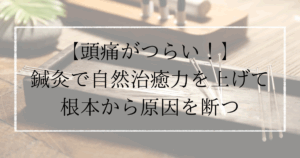
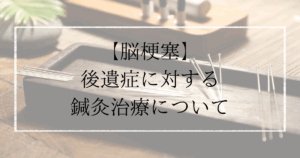
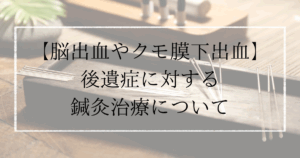
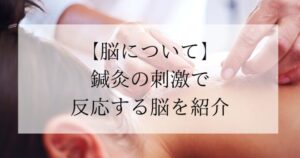
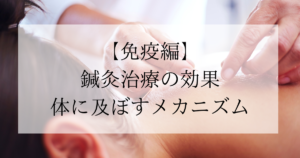
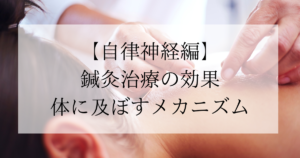
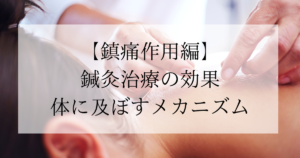
コメント